運営理念
保育理念・保育方針・保育目標
保育理念
- 保育を必要とするすべての子どもたち一人ひとりを大切にし、生きる力を育んでいきます。
- 保護者の気持ちに寄り添い、共に育ち合っていきます。
- 地域に根ざした子育ての発信基地として保育を実践していきます。
保育方針
命を大切にし、心身ともにたくましく、じぶんの力で未来を切り拓いていく意欲と主体性のある子どもを、集団生活を通して育てていきます。
保育目標
「たくましく」
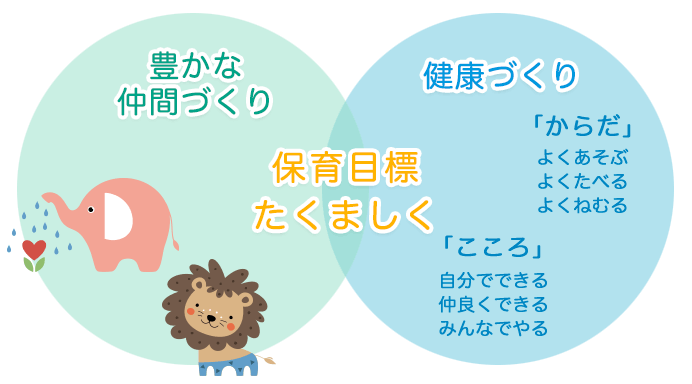
年齢目標
0歳児(たんぽぽ)
- 母乳、ミルクから食事へ移行していく
- 手づかみで食べる
- ハイハイをたくさんして遊ぶ
- 自分で立ち上がる力を、つけていく
- 着実に段階をおって、歩くことにつなげていく
- 手をたくさん使う
- 喃語(アーウー、ブー)から意味のある言葉になる
- 友だちが大好きになる
個人差があるので、長い目で見守っていく
1歳児(たけのこ)
- スプーンを使って食べる
- 歩行が確立し、全身をたくさん使って遊ぶ
- 腕や手をたくさん使う
- 道具を使って遊ぶ
- 自我が芽生え、自己主張を充分にする
- 言葉が広がり、獲得する(一語文~二語文)
- 友だちが好きになり、気の合う子ができる
オムツはずしは個人差があるので、ゆっくりとみていく
2歳児(くるみ)
- 食事、排泄、着脱など、基本的な生活習慣を身につける
- 体をたくさん動かし、手足を充分に使う
- 自分の要求を言葉で伝えようとし、話すことを楽しむ
- 自分でやろうとする気持ちを持つ
- 友だちと遊ぶ楽しさを知り、関わりを持つ
3歳児(まつぼっくり)
- 生活習慣の基礎がつくられる
- 人の話を聞くことができる
- 自分の要求を言葉で伝える
- 外で元気に遊ぶ
- 友だちと遊ぶ楽しさを知り、関わりが拡がる
4歳児(しいのみ)
- 生活習慣の基礎の確立
- 人の話を聞き、理解する
- 自分の考えを言葉で伝える
- 体を使って元気に遊ぶ
- 友だち関係を拡げ、いろいろな活動を体験する
5歳児(くすのき)
- 生活習慣の自立
- みんなで話し合い考えあう
- 体を充分に使いこなす
- 園生活を通して仲間意識をもち、自主的に活動する
つぼみ保育園の取り組み
特色ある保育
- ひとりの子どもを全職員で保育をするという姿勢を持ち、きめ細やかな対応を行っている
- 広い園庭で日常的に体を動かし、ダイナミックに外遊びを展開している
- 伝承文化を大切にしている
- 外部より講師を招き、健康体育を行い、しなやかでたくましい体づくりを行っている
- わらべうたを導入し情緒を育んでいる(講師による指導あり)
- 低年齢時より絵本を取り入れている
- 年中児よりお泊まり保育を実施している
発達過程とクラス相関性
- 6年齢別に園生活を送るが、保育方針の8つの発達段階を前提に年間指導計画が成されている。また子ども一人ひとりの成長段階を踏まえ、養護と教育が一体となり保育は展開される。
社会的責任
- 児童福祉施設として、子どもの最善の利益を守り、家庭との連携のもとに保育を行う。また保護者支援と合わせ、地域の子育て家庭に対する支援を行い社会的役割を果たす
- 適切な法人施設運営
- 人権尊重(児童福祉法)
- 保育の説明責任
- 個人情報保護
- 苦情解決(第三者委員設置)
健康支援
- 年間を通して薄着保育を主体に、素足で過ごす。外気にあたって皮膚を丈夫にする
- 子どもの健康状態ならびに発育・発達状態の把握
- 定期的・継続的に日強に応じて随時把握
- 登園時、保育中を通しての観察・保護者への連絡・嘱託医と相談
- 不適切な養育・虐待等の発見と適切な対応・関係機関との連携
- 健康増進
- 嘱託医による定期的健康診断(内科・歯科検診)
看護師の専門的対応
- 託医による内科健診、歯科検診、異常が認められたときの適切な対応
- 子どもの状態などに応じて保護者に連絡・嘱託医と相談
- 感染症の予防と適切な対応
栄養士の専門的対応
- 年齢別発達段階に応じて必要な栄養量を考慮した献立作成
- 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人ひとりの子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応する
食育の推進
- 食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画その評価及び改善に努める
- 子どもと調理員の関わりや、調理室などの食に関わる保育環境に配慮する
- 給食委員会を設置し、食育イベントを企画し分かりやすく伝えていく
安全対策・事故防止
- リスクマネージメント委員会を設置し、安全管理、事故防止に取り組んでいる(気づきメモの提出・分析)
- 避難、消火訓練の実施(毎月)
- 年2回の消防設備点検
- 交通安全教室の実施
- 不審者対応訓練の実施(年3回・1回は警察の指導)
- 救急救命シミュレーション訓練の実施
- SIDSの予防と対応を行う
- 緊急時に保護者へ、一斉にメールを送信
- 災害時に市との情報交換手段としてPHSの設置
- エピペン講習の実施
保護者への支援
- 入園前の面談を園長、主任、担任、看護師、栄養士の専門職が参加し、保護者の意向や子どもの状況把握をきめ細やかに行っている
- おたより帳や日々の対話を大事にし、家庭訪問、個人面談なども行っている
- 育児相談は保育士だけではなく看護師・栄養士も対応している。また必要に応じ、専門の先生との育児相談日をもうけている
- 苦情解決のシステムがあり、保護者の要望などに応えている
小学校との連携
- 児童要録による小学校との連携・年長児の小学校訪問
- 小学校の行事への参加(入学式等への出席)
- 職場見学の受け入れ
地域への支援
- 育児講座(年3回)
- 高齢者との交流(年10回)
- 出前保育(年6回)
- 小学生との交流(年6回)
- 情報誌「こんにちは!つぼみ保育園です」発行(年10回)
- 中学、高校生の職場体験
- 実習生、ボランティアの受け入れ

